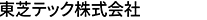出生率ではなく、成長を見守るデンマークにみる
家族支援政策の構造
2025年10月22日
海外流通トピックス
■業種・業態:全業種
■キーワード:養育費/社会的保障/幼児教育/育児休業

日本で最も大きな社会問題はといえば、人口減少や社会保障に関わる人口問題といえるでしょう。流通業界に限ることではありませんが、人手不足が深刻化しているだけでなく、市場の縮小によって商店数の減少が続いています。
ヨーロッパも少子化傾向が続いている中、比較的高水準を維持しているのがデンマークです。Eurostat(EU統計局)の2023年のTFR※(合計特殊出生率:15〜49歳の女性が一生のうちに平均して何人の子どもを産むかを示す指標)によれば、デンマークは2013年には1.67、2023年時点でも1.50とEU平均(1.38)を上回っています。
かつて「少子化対策の優等生」といわれていたフランスが2013年の1.99をピークに減り続け、2023年は1.66とTFRの急落に直面する中、デンマークは1.5台を維持し続けています。その安定性は、「子育ては公共の責任」という理念が国民の生活に根づいていることの表れです。シングルマザー支援の厚みもその一端を担っています。
養育費の公的回収、個人責任から社会的保障へ

日本では、シングルマザー(母子家庭)の貧困率が高いことが、明らかになっています。厚生労働省の「2023年 国民生活基礎調査」によると、2021年の子どもの貧困率は11.5%でした。わずかに改善傾向にあるものの、依然として約9人に1人が貧困状態にあるという事実は変わらず、構造的課題として残っています。
子どもがいる世帯で「大人が一人」の場合の貧困率は44.5%と半数近く、「母子世帯」の40%は生活が「大変苦しい」といい、「やや苦しい」と合わせると75%にも上ります。
この要因として次の2つが挙げられます。2021年度の「全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯で養育費を受け取っていない割合が約72%であることと、シングルマザーはパートなど非正規雇用率が約39%と高くなっていることです。特に養育費の未払いが7割にも上っているのは残念なことです。
デンマークでは、養育費の未払いを個人間の問題として放置せず、国家が介入して回収・保証する仕組みを整えています。
回収の流れとしては、養育費が未払いになると、子どもへの支援が途切れないように公的機関が立て替えて支給。その後、行政が債務者から回収(給与天引き・税還付との相殺など強制力あり)。支払い能力がない場合でも、支払いの計画を立てて分割返済することが義務づけられています。
この仕組みは、単なる「立て替え」ではなく、子どもの権利を社会全体で守る制度になっているのです。
養育費の公的回収を行っているのは、デンマークだけではありません。スウェーデン、フィンランド、ドイツ、イギリス、フランス、米国、韓国などでも行われています。ただし、その内容には大きな違いがあります。
スウェーデン、フィンランド、ドイツは、デンマークと同じ立て替え制度です。
イギリス、米国、韓国は、養育費を支払う義務のある人から強制的に徴収する制度(給与天引き制度)です。フランスは立て替え制度と強制的な徴収制度の併用で、韓国では養育費一時緊急支援制度も整っています。
デンマークの制度整備とTFRの乖離

デンマークの少子化は、早くに始まりました。1970年代後半から1980年代前半にかけてTFRの低下が急激に進行し、1983年には史上最低のTFR1.38を記録しています。この背景には、仕事と家庭の両立の限界がありました。
早くから産休が整っていて、1960年に法定化されたデンマークの産休制度は、すべての女性労働者に対し、雇用主負担による所得補償付きの14週間の母体保護休業を制度として保障するものであり、育児支援制度の前段階として位置づけられています。
1960年代半ばからは保育も開始しており、デンマークは保育の世界のフロントランナーです。1976年には親の仕事や介護の両立を支援するという明確な目的を掲げて、地方自治体に、働く世帯に保育を提供する「育児保証」を義務としたのです。
しかし、この制度が整備されたことにより、女性の就業率が急上昇して出産年齢が上昇するとともに、TFRは1.5〜1.7にまで低下、そして1983年には1.38まで落ちました。制度は整っているのに、子どもが増えないという状況に陥ったのです。
その要因を調べると、制度が「childcare(保育・預かり中心)」に偏ると、親子で過ごす時間が欠如し、2人目にはつながらないことがわかってきたのです。もちろん、社会的選択としての「子どもを持たない自由」が浸透していったこともあります。
デンマーク政府はこれに対応して、育児休業制度の拡充、公的保育施設の普及などに取り組みました。
保育から幼児教育とケアの転換

1984年、デンマークは育児休業制度を導入し、自治体による所得補償付きで、父母の双方が育児休業を取得できるようになりました。その後も制度改革を重ね、1997年には育児休業が32週間から最大46週間まで延長可能となりました。さらに2006年と2009年には、出産・養子縁組に関する休業と給付制度を一本化しました。
育児保証は2004年、両親の雇用状況に関係なく、生後26週からのすべての子どもを保育所へ通わせるようにしました。手頃な価格で、質の高い保育が受けることができるようになったのです。最低所得者には保育料を全額補助し、ひとり親や複数の子どもを持つ家庭には追加の補助があります。
これが実現したのは、ECEC(Early Childhood Education and Care:幼児教育とケア)という考え方が根ざしていることが大きいといえます。
ECECについては2006年に、OECD(経済協力開発機構)の『Starting Strong II』(「OECD幼児教育・保育白書 第2部」)で発表されています。ここでは「childcareからECEC(Early Childhood Education and Care:幼児教育とケア)」への転換を提言しています。保育制度は単なる就労支援ではなく、教育的・文化的実践であると再定義されたのです。
つまり、childcareは親の就労支援のためのものであり、ECECは子の育ち支援+教育という子どもの市民形成・教育的投資へと移行したということです。
日本でも最近は、「預かる」から「育む」という表現で語られています。
有給育児休業が1年に延長

デンマークでは政策効果により、1980年後半からTFRはV字回復。1.8前後になり、2008年には1.89まで上昇しました。しかし、2010年以降、ライフスタイルの多様化や晩婚化により、再び1.5台に低下しました。
2020年代には少子化が再び国家的課題になりました。「EUワークライフバランス指令」(加盟国に対して父母それぞれに最低4カ月の育児休業を割り当て、そのうち2カ月は譲渡不可とすることを義務化)に対応するかたちで、2022年に育児休業制度の大幅な改革を行いました。この指令により譲渡不可の育休枠を設けることで、父親の育児参加を促す構造が整えられたというわけです。
デンマークでは、その前から父母ともに46週間の有給育児休業がありました。それを父母から家族に変え、有給育児休業は1年(52週間)に延長しました。子どもが生まれる前に、母親は有給で4週間の出産休業があり、子どもの誕生後、各親に24週間の育児休業があることで、計52週間の有給育児休業が保証されています。このうち9週間は父親にしか使えない育休が割り当てられました。これが奏功して、父親の有給取得が増大しました。
育児休業手当は国家予算による税収でまかなわれているため、会社員だけではなく、自営業者、学生、失業者なども条件を満たせば対象となるのも大きな特徴です。
さらに、ひとり親向けに異なる育児休業制度も導入しています。片親が子どもの共同親権を持っていない場合、1人で46週間の休業を取得する権利があります。
さらに2024年1月から、ひとり親は「社会的親」と呼ばれる祖父母や兄弟などに最大13週間の休業を譲渡することもできるようになりました。子どもが生後1年の間に両親が離婚した場合、夫婦だったときと同じ育児休業の権利があります。
ちなみにデンマークでは、精子提供で出産する「選択的シングルマザー」が増えているそうです。ひとり親への手厚い保護があるのも背景にあるといえそうです。
以上、日本で大きな社会問題となっている少子化対策や子育て支援。デンマークの家族支援政策は、単にTFR向上を目的とした少子化対策ではなく、暮らしの質と子どもの権利を支える福祉政策として位置づけられています。これまで見てきたように、「家族支援・育児休業制度」「教育・保育制度」、そして保育施設の利用料補助なども含まれる「子ども手当・福祉制度」の三本柱が、生活の基盤を保証し総合的な支援になっていることがわかります。
※TFR(合計特殊出生率、Total Fertility Rate)とは、一人の女性が一生のうちに産む子どもの平均人数を示す指標です。15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計して算出され、人口動態の分析や少子化対策などの政策立案に用いられます。人口が自然に減少せず維持されるには、TFRが2.08程度必要とされています。
(文)経済ジャーナリスト 嶋津典代
発行・編集文責:株式会社アール・アイ・シー
代表取締役 毛利英昭
※当記事は2025年9月時点のものです。
時間の経過などによって内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。