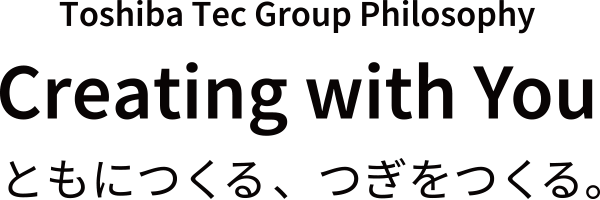リテールテックJAPAN東芝テックブースレポート
人手不足対応などのソリューションで
わくわくする“あたらしいかいもの”を提案

リテールテックJAPANは流通・小売業向けの情報システムと最新技術が一堂に集う国内最大の展示会です。人手不足への対応や環境負荷の低減、消費者ニーズの多様化など、小売店・飲食店が直面する課題解決に向け、東芝テックグループフィロソフィである「Creating with You ともにつくる、つぎをつくる。」をテーマにした今年の東芝テックブースの見どころをレポートします。
コンセプト展示
これまでにない一歩先の量販店、飲食店像を提案
今年の東芝テックブースでまず注目したいのは、量販店ソリューションと飲食店ソリューションの2つのコンセプト展示です。量販店ソリューションの展示では、カゴを預けることでレジ待ちの列を作らずに会計できる「Skip the Line Checkout(スキップ・ザ・ライン・チェックアウト)」を紹介しています。レジ待ちの列は、お客様の不満やチェッカーのストレス、さらには店内回遊性の低下を招くため、大きな課題となっています。Skip the Line Checkoutのユニークな点は、お客様のスマートフォンと二次元コードで紐づけた買い物カゴを預けることで、行列を不要にする仕組みです。
ミニチュア模型の展示では、買い物カゴが順次、手が空いたチェッカーのもとへ自動搬送される仕組みを紹介。これにより、新人チェッカーでも自分のペースで無理なく商品をスキャンできるようになります。また、お客様は待ち時間を活用し、近隣店舗での買い回りを済ませられるため、商業施設全体の回遊性向上も期待できます。
さらに受け取り用コールドロッカーと組み合わせることで、出勤前にモーニングセールで買い物を済ませ、退勤後に支払いを完了して商品を受け取るといった新しい買い物体験も可能になります。
東芝テックは3年後の実用化を見据え、Skip the Line Checkoutの開発を進めています。今後、買い物カゴカバーなどの関連需要が生まれることも予想されます。
Skip the Line Checkout

ミニチュア模型の展示では、買い物カゴが順次、手が空いたチェッカーのもとへ自動搬送される仕組みを紹介しました。
飲食店ソリューションでは、スタッフを介さず、お客様自身が入店から着席、会計までスムーズに行える『お客様エスコートシステム』を提案。人手不足という大きな課題に直面する飲食業界では、さまざまな省人化ソリューションが登場しています。しかし一方で、省人化はサービスの差別化を難しくする側面もあります。『お客様エスコートシステム』において、東芝テックが特に意識したのは、省人化とホスピタリティの両立です。
今回の展示では、大型ディスプレイによるセルフチェックイン、レーザー光でフロアに投影された矢印によるテーブルへの誘導、卓上タブレットを活用したキャンペーン・イベント情報の配信とオーダーの受付、さらにはスマホや自動走行ロボットによるセルフ決済などを組み合わせ、遊び心あふれるソリューションを紹介しました。来場者の反応は上々で、特にディスプレイとレーザー光の矢印を組み合わせたセルフチェックインは、クリニックなど異業種からも大きな注目を集めました。
また飲食店のスマホ決済には、お帰りのお客様が会計を済ませたかどうかが分かりにくいという課題がありました。今回の展示では、会計後のお客様を入店時とは異なる色の矢印で出口へ誘導することで、会計済みであることを明確に視認できるアイデアも紹介されました。
お客様エスコートシステム

ディスプレイとレーザー光の矢印を組み合わせたセルフチェックインは、クリニックなど異業種からも大きな注目を集めました
量販店ソリューション
よりスムーズなセルフ決済へ さらに進化したセルフレジ
通常レジ、フルセルフレジ、ピピットセルフなど、コーナー別に展示が行われた量販店ソリューションの中で、最も賑わいを見せたのは、やはりフルセルフレジに関する機能やソリューションを紹介するコーナーでした。まず注目したいのは、アテンダントに代わって空きレジへスムーズに案内する『空きレジ案内システム』です。
近年、セルフレジの導入が進む中で、自動釣銭機を搭載しないキャッシュレス専用機の普及が拡大しています。しかし、多様なチェックアウト方式が混在する混流会計は、アテンダントの負担を増やし、お客様の混乱を招く要因にもなります。そのため、キャッシュレス専用機と現金対応機を分けて運用するのが一般的です。
『空きレジ案内システム』は、セルフレジ上部に設置されたネットワークカメラの映像などを活用してレジの使用状況を把握し、決済方法(キャッシュレス決済、スマホ決済、カート決済、現金決済など)に応じて、対応するセルフレジへご案内するソリューションです。
このシステムの最大のメリットは、決済方法ごとに専用スペースを設ける必要がなくなる点にあります。スムーズな混流会計の実現により、省スペースで効率的なセルフレジ運用が可能となることが期待されます。
フルセルフレジ

アテンダントに代わって空きレジへスムーズに案内する『空きレジ案内システム』が注目されていました
ネットワークカメラ映像の分析性能の進化も、注目すべきポイントです。セルフレジ利用時の不正な処理をリアルタイムで検知し、アテンダンドに通知する機能や、レジでの忘れ物をお客様に知らせる新機能が、今後登場する予定です。
フルセルフレジ不正検知システム
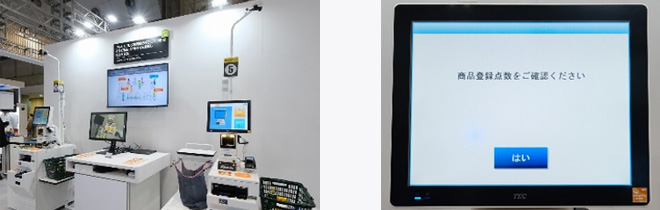
セルフレジを利用した時にスキャンされていない商品をリアルタイムで検知してアテンダンドに通知してくれます
セルフレジ導入において、アルコールなど20歳未満への販売が禁止された商品の対応も重要な課題の一つです。この課題に対するソリューションが、画像解析AIによる年齢推定とOCR技術を活用した身分証の読み取りを組み合わせ、リモートオペレーターが年齢確認を行う『リモート20禁解除システム』です。このシステムにより、従来はアテンダントによる視認が必要だった年齢確認の負担を大幅に軽減できることが期待されています。
また『セルフレジ 商品券読取装置連動』も大きな注目を集めた展示の一つでした。多種多様な商品券への対応は、チェッカーが自店舗で使用可能な商品券を覚える必要があるため、従来から量販店にとって課題となっていました。この課題を解決するのが、OCR技術による商品券の読み取りと利用可否の自動判断を行う本製品です。最大の特徴はコンパクトな設計であり、有人レジに接続することで、従業員教育の負担を大幅に軽減することが可能です。
さらに、売場移動型セルフレジ『ピピットセルフ』の進化にも注目が集まりました。その一つが、重量センサーの検知能力向上です。これまで検知が難しかった軽量商品も識別できるようになり、商品スキャン忘れを防ぐアラート精度が向上。これにより、意図せず万引きをしてしまうリスクの回避にもつながります。
また、モニター画面に登場するキャラクターに応じた音声を設定できる機能も新たに追加されました。展示では、オリジナルキャラクター「ピトセちゃん」が操作方法を解説するデモンストレーションが行われ、親しみやすい声による情報提供が、これまでピピットセルフを敬遠していた層への普及を後押しすることが期待されています。さらに、お会計前に店員確認バーコードを読み込むことでアテンダントが取引明細を確認できる新機能も追加され、セキュリティ面での向上が図られています。
ピピットセルフの画面は、新たな販促メディアとしても大きな注目を集めています。しかし、その性質上、購買履歴に基づくレコメンド機能にはプライバシーの観点から慎重な対応が求められます。この課題に対応する新機能として今回搭載されたのが、『コトダク連携』です。共創パートナーであるスコープが開発した「コトダク」は、その日の気分に応じたキーワードを選択することで、メニューや食材を提案するサービスです。特売情報と連携することで、店舗の新たな魅力創出につながることが期待されます。
ピピットセルフ

量販店ソリューションのコーナーでは、連日多くの来場者がピピットセルフの新機能を体験しました
データソリューション
香りへの反応を可視化しマーケティングにフィードバック
電子レシートサービス『スマートレシート』のデータ分析や、カート/スマホPOSへのリアルタイム販促など、東芝テックのデータソリューションを紹介するコーナーで注目されたのが、香りに関する消費者の反応を可視化する『香りリテールメディア』です。
化粧品や芳香剤など、香りが消費者の購買意欲を左右する商品は少なくありませんが、これまでは香りに対する反応を定量的に把握する手段がありませんでした。『香りリテールメディア』の特徴は、大きく二つあります。一つ目は、消費者が多様な香りを嗅ぎ分けられる点です。化粧品の場合、これまではテスター(試供品)を使って香りを確認するのが一般的でしたが、実際に肌に塗ると複数の香りを嗅ぎ分けるのが難しいという課題がありました。指示に応じて香りを噴出する『香りリテールメディア』を使えば、消費者は納得いくまで香りを比較することができます。
二つ目は、ネットワークカメラの画像分析により、「商品をカゴに入れた」などの購買行動データを蓄積できる点です。これにより、従来は難しかった香りの定量的な評価が可能になります。また、香りが購買行動に影響を与えるコーヒーのプロモーションなど、食品マーケティングの分野への応用も期待され、来場者から大きな注目を集めました。
香りリテールメディア

香りが購買行動を左右する食品マーケティングの観点でも来場者の大きな注目を集めました
飲食店ソリューション
省人化ニーズに対応する多様なソリューションを展示
飲食店ソリューションでまず注目したいのが、クラウド型POS『FSlegatony(エフエスレガトニー)』です。クラウド型POSシステムは、導入が容易というメリットがある一方で、対応ハードウェアがタブレットなどの汎用品であるため、ハードウェアに関するトラブル対応という新たな負担が店舗に生じることが一般的です。人手不足という大きな課題に直面する飲食店にとって、この点がクラウド型POS導入への不安材料となっていることは否めません。
FSlegatonyと従来のクラウド型POSの最大の違いは、クラウドサービスによるソフトウェアと、堅牢で耐久性に優れた東芝テック製専用ハードウェアの双方を提供する点です。ハードウェアのトラブルには、東芝テックのサービスネットワークが迅速に対応するため、従来のPOSシステムと同様の運用が可能です。もちろん、店舗のデータ分析やマスタ作成がいつでも、どこでもできるクラウドサービスのメリットも十分に活かすことができます。
クラウド型POS FSlegatony

クラウドサービスと、堅牢で耐久性に優れた東芝テック製専用ハードウェアを採用することで、安心・安全な運用が可能です
また、飲食店向け無線オーダーシステム『Order Velocity』との連携により、オンプレミス型の安定性や使いやすさを保ちながら、クラウドサービスの最新機能を追加料金なしで利用できる点も注目したいポイントです。飲食店向け注文連携サービス『OrderLinkage(オーダーリンケージ)』との連携により、フードデリバリーやモバイルオーダーなどの外部サービスと接続し、注文管理を一元化することも可能です。FSlegatonyは、東芝テックのモバイルPOSレジ『POSasy(ポサシー)』との一元的な運用も可能です。多店舗展開では、店舗規模などに応じてFSlegatonyとPOSasyを使い分け、本部が売上を一元管理するという提案もおすすめです。
デリバリーやモバイルオーダーの普及に伴い、多くの飲食店にとって、これら外部サービスの活用は避けて通れない課題となっています。その一方で、外部サービスとの連携は、端末に表示された注文内容を手作業でオーダーシステムに入力するなど、店舗スタッフの負担増加や業務の複雑化にを招いています。グローバルリテールプラットフォーム『ELERA』経由で、外部サービスからの注文をPOSと自動連携するのが、ELERA注文連携サービス「OrderLinkage」です。
そのメリットとしてまず挙げられるのは、外部サービスごとに用意されていた管理端末を1台に集約できる点です。注文内容をハンディターミナルに再入力する必要がなくなったことも重要なポイントです。キッチンプリンタから出力される伝票には、配達番号や受渡時間などの注文情報が自動で印字されるため、ケアレスミスの削減にも大きな役割を果たします。2022年のサービス提供開始以来、連携する外部サービスの拡充が進んでおり、今後も店舗スタッフの業務省力化に大きな貢献をし続けることが見込まれています。
飲食店の省力化に大きな役割を果たすのが、お客様自身が注文を行うことでフロアスタッフによる注文業務を大幅に軽減するセルフオーダーシステムです。セルフオーダーには、店舗側が配備したタブレット端末を利用する方法のほか、卓上のQRコードをお客様がスマートフォンで読み取るモバイルオーダーがあります。東芝テックが今年1月に発売した飲食店向けモバイルオーダーシステム『OtegaruOrder(オテガルオーダー)』の最大の特徴は、OrderLinkageの機能を利用することで、従来のハンディターミナルによる注文との併用が可能になる点です。
人手不足という課題がある一方で、フロアスタッフによる温かみのある接客を大切にする飲食店は少なくありません。“オテガル”の名の通り、お客様のスマートフォンによるセルフオーダーと従来のフロアスタッフによるオーダーを統合できることが、OtegaruOrderの最大の特徴です。少しでもフロアスタッフの負担を減らしたいと考える飲食店にとって、タブレット端末などの設備投資をせずに運用を開始できるOtegaruOrderの提案は、大きな意味を持つでしょう。
ELERA注文連携サービス「OrderLinkage」

フードデリバリーやモバイルオーダーなどの外部サービスと連携し、注文管理を一元化できます
飲食店向けモバイルオーダーシステム「OtegaruOrder」

お客様のスマートフォンによるセルフオーダーと従来のフロアスタッフによるオーダーを統合できます
専門店ソリューション
1台のスマホでOMOを実現するソリューションに注目
アパレルに代表とする専門店では、近年、オンラインとオフラインを融合させるOMO(Online Merges with Offline)マーケティングや、実店舗で品切れ商品を即座に自社ECサイトで注文できるエンドレスアイルへの対応が急務となっています。専門店向けソリューションで最も注目されたのは、これらの課題にスマートフォン1台で対応できるOMO支援Webアプリ『Shop Unify(ショップユニファイ)』です。
アパレル店舗では、サイズ切れによる販売機会の損失を避けることができないのが現実です。これまでは、サイズ切れが発生した場合、近隣店舗に電話で在庫を確認したり、PCで商品管理システムにアクセスして在庫を確認する必要がありました。Shop Unifyを使えば、接客中でもスマートフォンで在庫状況を確認できます。また、他店舗の在庫をお客様の住所に配送したり、ECサイトでの注文を店舗で取り置きすることや、インターネット経由でBOPIS(試着予約)に対応したりすることも、スマートフォン1つで可能です。これにより、販売機会の損失が減少し、在庫の効率化が期待されます。
子供服を企画・販売するナルミヤ・インターナショナル様もShop Unifyのユーザーです。ブースで紹介された事例動画では、他店舗の在庫を購入するお客様の8割が、店舗取り寄せではなく自宅配送を選んだことに驚かされたといいます。送料無料キャンペーン期間中という特殊な条件を考慮しても、実店舗とオンラインの連携には、これまで予想されていた以上の大きな可能性があると言えるでしょう。
OMO支援Webアプリ「Shop Unify」

接客中でもスマートフォンで在庫状況を確認できるため、販売機会の損失を減らし、在庫の効率化が期待されます
店頭注文端末『Shop Unify Self Interacetive(ショップユニファイ セルフインタラクティブ)』は、店舗に設置された大型サイネージを通じて、お客様自身がShop Unifyの機能にアクセスできるソリューションです。今回の展示では、アバターによる商品提案という新しい買い物体験が提案されましたが、今後はパートナーとの連携により、さまざまな機能強化が予定されています。
店頭注文端末「Shop Unify Self Interacetive」

店舗に設置した大型サイネージを通じて、お客様自身がShop Unifyの機能にアクセスできるソリューションです
そのほか、専門店のニーズに対応する東芝テックのクラウド型POSシステム『ShopTrust(ショップトラスト)』も注目を集めました。クラウド型ならではの特徴であるリアルタイムでのデータ管理は、閉店後の作業効率化だけでなく、商品開発やマーケティングにおける販売データ活用にも大きな役割を果たします。特にアパレル事業の経営においては、売上状況に応じた仕入れ判断が重要です。クラウド型POSシステムによる販売実績の可視化は、仕入れ判断の迅速化にも大きな貢献が期待されます。
クラウド型POSシステム「ShopTrust」

クラウド型POSシステムによる販売実績の可視化は、
多方面にわたるメリットが期待されています
店舗内のデジタルサイネージやディスプレイをリテールメディアとして積極的に活用する提案が行われたことも、今回の展示の大きなポイントの一つです。注意深く観察すると、展示ブース内の各種ディスプレイ端末がそれぞれ異なるサイネージ広告を表示していたことに気づいたでしょう。自社が保有するデータに基づき、自社Webサイトやアプリ、店舗ディスプレイで広告を配信するリテールメディア活用は、量販店、専門店、飲食店を問わず、大きな課題の一つです。その一例として行われた店舗ディスプレイの活用提案は、これからのリテールメィアのあり方を考えるうえで重要な役割を果たしたと言えます。
リテールメディア活用

展示ブース内の各種ディスプレイ端末には、サイネージ広告が表示されていました