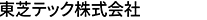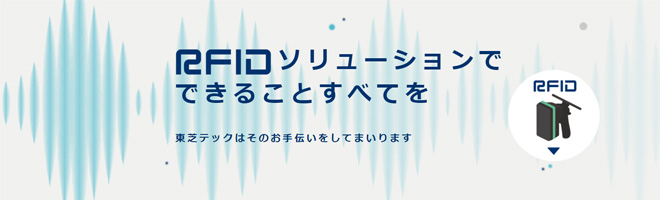RFIDセルフレジ導入事例
将来、二人だけでも店を運用できるような仕組みを
模索する中で出会ったのがRFIDセルフレジでした
株式会社 藤林 「うさぎのうさばらし」

アウトレットショップ「うさぎのうさばらし」
RFIDセルフレジソリューション
-
導入時期
2023年10月
-
導入目的
人手不足の解決
-
課題
ライフステージ変化で退職するパート・アルバイトに頼らない店舗運営
店舗オーナーの高齢化に伴う若者中心の顧客とのギャップ
-
効果
レジ会計の大幅な省力化
ネット通販の“ロスト問題”や棚卸の効率化への期待
将来的な無人店舗への布石
地域の小規模店舗としては
初のRFIDセルフレジ導入
京都市の西隣に位置する亀岡市千代川町付近は、交通の利便性もあり、近年急速にベットタウン開発が進んでいます。国道9号線沿いの商業集積地の一角にあるアウトレットショップ「うさぎのうさばらし」は、2023年7月導入の福井県立恐竜博物館ミュージアムショップに続き、全国で2例目となる東芝テック製RFIDセルフレジが稼働を開始しています。
家具・インテリアやアパレル通販を軸に事業を展開してきた藤林 重麿・麻里夫妻が同店を出店したのは2023年10月のこと。RFIDセルフレジに注目した理由を重麿氏はこう説明します。
「新店オープンにはスタッフが不可欠ですが、せっかく仕事を覚えても結婚や就職など環境の変化で辞めてしまわれます。人手不足が今後さらに深刻化すると見られる中、最終的には夫婦二人だけで事業を続けられる方法を模索する中、出会ったのがRFIDセルフレジでした」
麻里氏が大手衣料量販店で買い物をしたことが、RFIDセルフレジの存在を知ったきっかけでした。
「置くだけで商品を読み取るレジがあると聞いたときは、どういう仕組みかまったく想像ができませんでしたが、私たちが感じている課題解決に大きな役割を果たすと直感しました。ネットで調べ、POSレジとRFIDの連携ソリューションを提供する2社にコンタクトを取り、POSレジ機能が我々のニーズにフィットする東芝テックのRFIDセルフレジ導入を即決しました」
導入にあたり重麿氏が要望したのは、先行していた恐竜博物館の仕様より一回り大きい、標準的な買い物かごサイズへの対応でした。
「アウトレットショップの商品は多様で、複数商品をまとめて買われる方も多いことを考えると、食品スーパーでも利用される標準的な買い物かごサイズへの対応は不可欠と考えました。電波強度や干渉の問題もあり、仕様変更は簡単なことではないことは後で知ったのですが、東芝テック営業担当の方の尽力もあり無事オープンに間に合わせることができました」


RFIDタグをあらかじめ用意し効率的なタグ付けを実現
オープンにあたりRFIDセルフレジ1台と対面式セルフ1台を導入した同店では、ほぼ9割のお客様がセルフレジを利用しているといいます。店頭で接客販売を担当する麻里氏はこう説明します。
「特にご高齢の方の場合、自分でバーコードを読み取るセルフレジは苦手という方も珍しくありませんが、RFIDセルフレジはそうしたことはほぼなく、スムーズにご利用いただけています。サポート役の店舗スタッフについても、特に教育の必要もなく、すぐに運用できています。長年アパレル業界で仕事をしてきたこともあり、個人的には洋服を丁寧に畳んでお客様にお渡ししたいという思いもあるのですが、ショッピングバッグの普及もあり、そうしたことを意識される方はむしろ少数派のようですね。対面式セルフについては、経験上、こちらの方がいいと私が判断したお客様を積極的に誘導する形で運用しています。やはり会計時の世間話もお店のファンを増やす上では大切ですからね」
RFID導入では、タグ発行の省力化も課題の一つです。
「当店の場合、オープン時の在庫は1万点弱で、その後も毎月1,000アイテム以上は入荷していますから、RFIDタグ付けをどう省力化していくかという点は当初から大きな課題でした。現在はトップスやバッグといった商品部門ごとに価格を印刷したRFIDタグをあらかじめ用意することで対応しています。RFIDプリンタで印刷したタグは百均ショップで見つけた容器で保管を行い、入荷の都度、それを商品に付けるという運用を行っています。サイズにも対応したかったのですが、その場合、用意するタグが飛躍的に増えてしまうため現在の運用に落ち着いています」

個人の小規模店舗の事業継続に大きな可能性を持つRFID
重麿氏が今後の課題として挙げるのは、RFIDを軸にした業務プロセス全体の改善です。
「導入後システム側のトラブルは一度も発生していませんが、一方ではタグを二つ付けてしまったり、付け忘れたりといったヒューマンエラーはすでに何度も発生しています。業務プロセスの見直しは今後も継続して行う必要がありますが、それでも我々のような小規模店舗にとり、RFIDのメリットは極めて大きいと感じています。個人事業主が60代、70代になっても自分のお店を持ち続けることは社会保障の観点でも大きな意味を持ちます。ところが近年の人手不足はそれを難しくしているというのが実情です。先方の都合で辞められる心配をする必要がないRFIDソリューションは、この問題の解決策になると考えています」
商店街としてRFIDセルフレジを導入し、レジ業務を一元化し、店舗無人化を可能にするというアイデアはその一例。重麿氏は、すでにRFIDゲートを導入することで時間帯によって自店舗を無人化する取り組みも開始しているといいます。
RFIDは事業のもう一つの柱である通販業務の改善にも大きな役割を果たします。

残りの1割は、対面式セルフで対応

対面式セルフで対応しています
「店舗は私たち夫婦に加えパート2名、アルバイト4、5名という体制で運営し、スタッフの皆さんには商品撮影など通販事業を中心に担当いただいています。我々に限らず、通販事業では、あるはずの商品があるべき場所にない“ロスト”の解消が大きな課題になっています。私たちもそれは例外ではなく、ひとたびロストが発生すると、通販事業の担当者が1、2時間掛けて倉庫内を探し回るという手間が発生するため、RFIDの探索機能はこうした業務のムダを大きく改善することが期待できます。私は今、50代半ば。将来的には、リアル店舗と通販の双方を夫婦二人で回していきたいと考えていますが、RFIDは我々の未来像に大きな役割を果たすと考えています」

※当記事は2024年4月時点のものです。
時間の経過などによって内容が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
この記事で紹介した商品 / 関連サイト